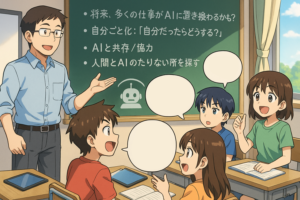本日までの3日間、出仲間こども園ではナイストライで、中学生2名の職場体験を受け入れています。
「ナイストライ」は、中学生が地域の職場等での働く体験を通じて、将来の生き方や進路を考え、社会で自立していく力を育む“キャリア教育”の一環として実施されています。
この3日間、2人は低年齢クラスに入って保育の仕事体験をしました。
後で感想を聞くと「楽しかった!」「子ども達がムッチャ可愛かった💖」などと中学生らしい感想を語ってくれました。
今回はそれに加えて、中学生の方から事前に疑問点を整理し、主幹保育教諭に質問する時間を求めてきた点が、これまでとは異なる特徴でした。
「主幹保育教諭はどんな仕事ですか?」「保育の仕事で一番大切なことは何ですか?」「どうして保育の仕事を選んだのですか?」等々…
中学生らしい質問が次々と投げかけられました。
きっと学校に帰ったら総合学習の時間等で、将来の職業について自分ごととして意見を出し合う時間を持つのでしょうね。
「自分ごと」と言えば、昨日下記のようなネットニュースの記事を見つけました。
公立小学校で「リーダー教育」大人の研修を小学生向けに3年間のプログラム (テレQ(TVQ九州放送)) – Yahoo!ニュース
福岡市の西高宮小学校で行われた、4年生を対象とした「リーダー教育」の授業の様子です。
そのねらいは、指示を待つのではなく、自分で考えて動ける力を育てること…
ここでいうリーダーとは、皆をぐいぐい引っぱる人という昔のイメージではなく、「周りに前向きな影響を与えられる人」と捉えられています。
記事では、「それぞれの人間が、自分や周囲に対して前向きな影響力を及ぼしていくことそのものがリーダーシップ」だと考える企業の例も紹介されています。
授業では「将来、今の仕事の多くがAIに置き換わるかもしれない」という前提で、将来について自分ごととして考える課題に取り組みます。
子どもたちからは「AIと共存する道を選ぶ」「人間とAIの足りない所を探す」「協力が大切」などの様々な意見が出たそうです。
AIにはできない「何かをしたい」という意志をどう自分の中で育てていくか…今回の授業は、課題から行動を生みだす訓練とも言えます。
前回の園だよりでは、未来の目標から現在を考える「ムーンショット計画」を紹介しましたが、これも似たような事例なのかもしれません。
小中学校と対象は異なるものの、教育・保育に携わる我々としても、子どもたちが未来を自分ごととして捉え 行動に移せるような“心の基盤”をどのように育てていくか…
今回のナイストライをきっかけに一層意識していきたいと思います。
※イラストは生成AIで作成しています。