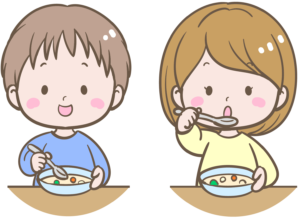今週から雨の日が続くようで、いよいよ梅雨の始まりでしょうか🌂
今までのように思いっきり外遊びができず、室内での遊びも増えるかも知れません…
ただ、室内遊びでは外遊びとはまた違った醍醐味が味わえます。
「人形劇」…かな?
そこには何かをイメージしながらひたむきに遊びに熱中する子ども達の微笑ましい姿があります😊
一人おままごとをしています。
何を作っているのかな?
保育者が牛乳パックで作ったイヌのオモチャがお気に入りです🐶
「シロ」という名前をつけて、さっそくお散歩しています!
室内遊びでは、外遊びより動きが少ない分、いろいろな事に集中してイメージを膨らませて遊ぶことができます。
仮面ライダー?戦隊?…それともロボット🤖
頭にはボウルのヘルメット、腕には円柱ブロックを装着し…変身完了✨
「かぁ~っこいい! ボクも変身!!」
彼らは足からアーマーを装着中です😆
「私はリングで変身よっ!」
これから雨の日でも子ども達がイメージを膨らませて、思いっきり遊べるような環境づくりに心掛けていきたいと思います。
「室内」つながりということで、今日は子ども達の食事と遊びの関係について一例を示したいと思います。
食べ物をスプーンですくって口へ運ぶ…
至極簡単なことのようですが、発達段階におけるこの時期の子どもさん達にとって、この行動を獲得するには様々な身体・認知機能の発達が必要とされます。
目でご飯を捉えて→握ったスプーンを持っていき→ご飯をすくって→手首や肘・肩を、腕の動きに合わせて柔軟に動かし→尚且つ食べ物が口に近づいた時にタイミング良く口を大きく開ける…
スプーンで食事をする行為だけ見ても、いろいろな身体・認知機能を統合的に連携させて操作するスキルが必要となります。
「自分でスプーンを使い ご飯を食べる」…そのためにはいろいろな身体的・認知的な育ちが必要と前記しましたが、これらは遊びの中でも育むことができます。
【目と手の協応】
前記の例でいいますと、「目でご飯を捉えて→握ったスプーンを持っていく」ためには、目と手を強調させて動かすためのスキルが必要です。
積み木遊び
積み木を積んだり、並べたり、形を作ったりする中で、目と手の協調、空間認識、創造力の発達が期待できます。
型はめ・パズル遊び
目と手の協調だけでなく、集中力や問題解決能力の向上に繋がります。
つまむ・挟む遊び
トングやアイクリップを使って小さな物をつまむことで手先が器用になり、スプーンをしっかり保持するための手指の筋力強化を促進します。
穴通し
穴の開いた容器に紐を通すことで手先に視線を集中させます。根気よくチャレンジし、通せた時の達成感が味わえます。
この他にも、お絵描きや粘土遊び、棒さし遊びなども目と手の協調を育む上で有効と言われています。
【腕や肩の運動機能の向上】
前記の例では、「ご飯をすくって→手首や肘・肩を腕の動きに合わせて柔軟に動かす」ための運動機能を高める遊びについてです。
大型の積木遊び
大型の積み木を積んだり、崩したりする遊びは、手と腕のコントロールを高めます。
特に、高く積み上げることを目指すと、腕全体の安定性が必要になり肩の可動域も広がます。
スプーンを使うということで手先の器用さに目が行きがちですが、体幹の育ちも必要で、 座った状態でバランスを取るための腹筋や背筋の強さ、身体が傾かないように支える姿勢保持なども必要です。
そう考えるとスプーンを上手に使うために必要なスキルは、身体・認知機能の統合力なのですね。
こうした身体・認知機能の連携が上手くいかないと、スプーンやお箸を上手く持てなくなったり、食べ物を口から取りこぼすようになるかも知れません。
…ただ、食事は「訓練」や「練習」をするものではなく、我々が生活の中でそのようなスキルを身につけるためのサポートをするべきだと思います。
「いらっしゃいませ~👨🍳👩🍳」
子どもは「食」に対する興味が強く、ままごと遊びでも お料理やお店屋さんごっこが大好きです。
おそらくそれは家庭や園において日常的に目にする機会が多いからなのでしょうね。
子ども達は興味を引くものに目を向け、目で追い…
興味があるから手を伸ばし、掴もうとします。
その中で手先や体全体を動かしながら、いろいろなスキルを身につけていきます。
目と手の協応や空間認知力の発達と共に、いろいろな道具も器用に扱えるようになってきました。
今回スプーンを例にとりましたが、やはり遊びには日常生活に必要なスキルを育むための 大切な要素が含まれているように思います。
これからも子ども達の心身の成長過程を見守りながら、その子に応じたオモチャや環境を用意していけるように研鑽を重ねていきたいと思います。