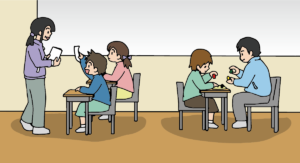「あなたは何故保育士になったのか?」
6月に入って保育士が園児をカッターで切りつける衝撃的な事件がありました。そして今週も、世田谷の保育士が園児の髪をのけぞるほど強く引っぱるなどの虐待をしたというニュースがありました。
どんな理由があったとしても許される行為ではないということは大前提として、どうしてこのような事案が後を絶たないのか?…当初は夢を持って憧れの保育士になった方たちだろうに、このような事件が頻発するたびに残念な思いにとらわれます。
本人の資質の問題?ゆとりのない勤務体制の影響?それとも職場の人間関係?…原因は定かではありませんが、同じ保育施設の人間として我々も決して人ごとではなく、考えさせられる事件です。
「あなたは何故保育士になったのか?」
保育者として子ども達に接するとき、必ずしも思い通りの保育ができず壁にぶち当たることもあると思いますが、そんなときは原点に立ち戻る自制心や心のゆとりが必要なのかも知れません。
「自分の努力不足を子どものせいにしてはいけない」…そう考えるのは、私もかつては支援学校の教師として教育に携わっていたからなのかも知れません。そういう経緯で、子どもとじかに接する保育士さんの気持ちは多少なりとも理解できるつもりでいます。
教師として壁にぶち当たって指導の取りかかりがつかめないとき、私も自分の心に問いかけたものでした。
「私は何故教師になったのか?」
私の教員生活の原点を振り返ったとき、職場で初めて同僚となった先輩の指導教官のことばが強く印象に残っています。
「子どもは毎日成長する。何も発見できないはずはない。毎日子ども達の様子に目を向け、小さな変化を見落とさないようにしなさい。」
思い通りにいかないとき、その原因を子どもに求めるのではなく、大切なことは、発達のゆるやかな子ども達に愛着を持って接し、丁寧に毎日の生活を見守る姿勢だと、その時感じました。
ましてや保育園の活発で生命力あふれる子ども達は、毎日が「成長」そのものです。
ちょっと目を凝らして見てみれば…
愛着を持って見守れば…
それこそ毎日が発見の連続だと思います。
私は保育士ではありませんが、実践家の一人だった者として、そうした子どもの姿を発見したら「子どもの発達ってすごい」と感じ、だからこそ そうした発達の芽を見逃さずに伸ばしていけるような手立てが必要だとも考えるでしょう。
先生方にはいつもそのような気持ちを大切に 子ども達を見守る姿勢を身につけてほしいと思っています。
そうした意味合いから、先生方には子ども達の姿を写真やブログ、ドキュメンテーションといった形で毎日残すように働きかけています。
子ども達に意識的に目を向けることを通して、彼らの成長や生き生きした姿に触れ、それが新たな気付きや支援のヒントになるかも知れません。同時に自分の職業の素晴らしさや やり甲斐を実感できる機会にもなるのではと思います。
その上で、保育者が子ども達と接する時間をできるだけ損なわずに、保育に携わることの楽しさやその意義を実感できるように、煩雑な事務作業の簡素化や行事の精選など…保育の環境を整えるのは、私たち管理職の役割だとも改めて感じました。