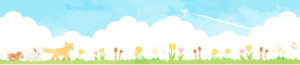今日はまるで季節が遡ったような寒い1日でした!
「寒の戻り」という言葉がピッタリの気候でした。
ただ、こうして一雨ごとに暖かな季節に向かっているのでしょうね。
最近のたんぽぽ組では、「おままごと遊び」が盛り上がっています。
特に子どもたちが夢中になっているのは「お料理ごっこ」です。
ケーキやジュース、野菜やごはんなど、身近な食べ物をイメージしながら、「まぜまぜ〜」「かけちゃう!」といった声があちこちから聞こえてきます。
それぞれが自分なりの“シェフ”になって、材料を選んだり、お皿に盛り付けたり、友だちに「どうぞ!」とごちそうしたり…子どもたちの表情はとてもいきいきとしています。
ごっこ遊びを通して、手先を使ったり、イメージを膨らませたり、友だちとやりとりしたりと、たくさんの学びが育まれています。
また、遊びのなかでお友だちのしていることに興味をもち、「いっしょにやろう」と言葉を交わす場面も増えてきました。
こうしたやりとりを通して、自然に社会性や思いやりの気持ちも育ってきているように感じます。
いつも思うのですが、子どもたちが自然と「料理」というテーマに向かって遊ぶのには、どのような心理的背景があるのでしょうか?
1歳〜2歳ごろの子どもたちは、保護者や保育者など自分の身近な大人の行動を注意深く観察し、それを真似しようとする「模倣欲求」が非常に強くなります。
また、料理遊びは「○○に見立てる」「○○のふりをする」といった象徴機能の初期段階と言われています。
例えば、スポンジをケーキに見立てたり、ボトルのふりをして調味料をかけたりする姿は、実生活の再現遊びなのかも知れません。
料理は「食べさせてあげる」「いっしょに食べる」という他者との関わりを伴う行為でもあります。
ごっこ遊びの中で「どうぞ」「ありがとう」などのやり取りが自然と生まれることは、社会性の発達や、思いやりの気持ちにつながっていくと思います。
さて、新しいお部屋に移動して二週間…
子どもたちは今まで触れたことのないオモチャに触れながら、好奇心の輪を広げています。
「面白いね~っ」「これはどうすればいいんだろう?」
子どもたちはパズルや積み木を手にいろいろと試行錯誤をして遊んでいます。
「おもしろ~い!」「速いよ速いよ~っ!😆」
遊び方も形にとらわれず、子どもたち独自のアイディアで面白いです!
「タコで~す🐙」(^0^)
「太鼓の達人🥁」
「ふう~、落ち着くなぁ~🛀」
オモチャには決まり切った遊び方はありません。
子どもたちの感じ方で、想像力のままにいろんな遊び方を投影することができます。
これからも、子どもたちが興味や関心をもって主体的に遊べる環境づくりを大切にしていきたいと思います。